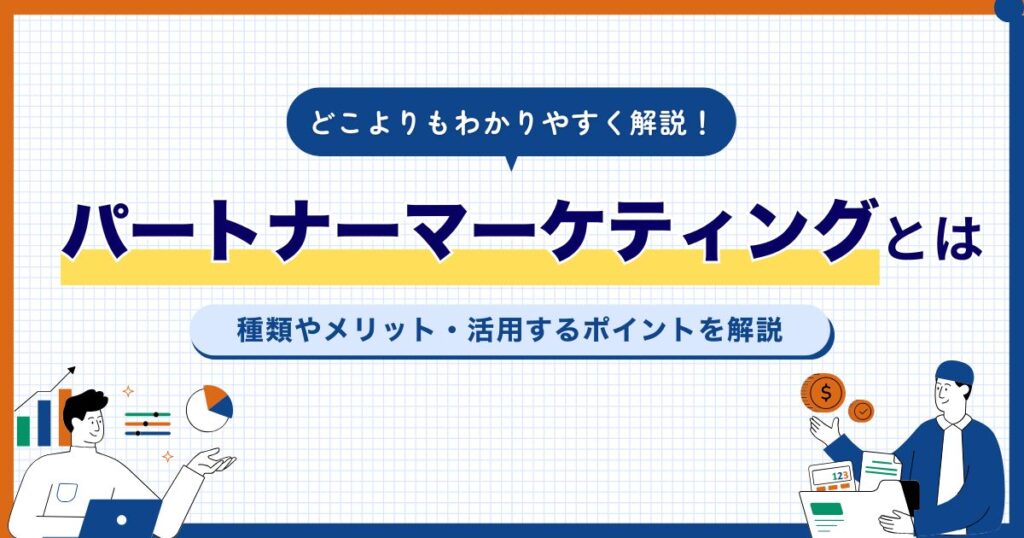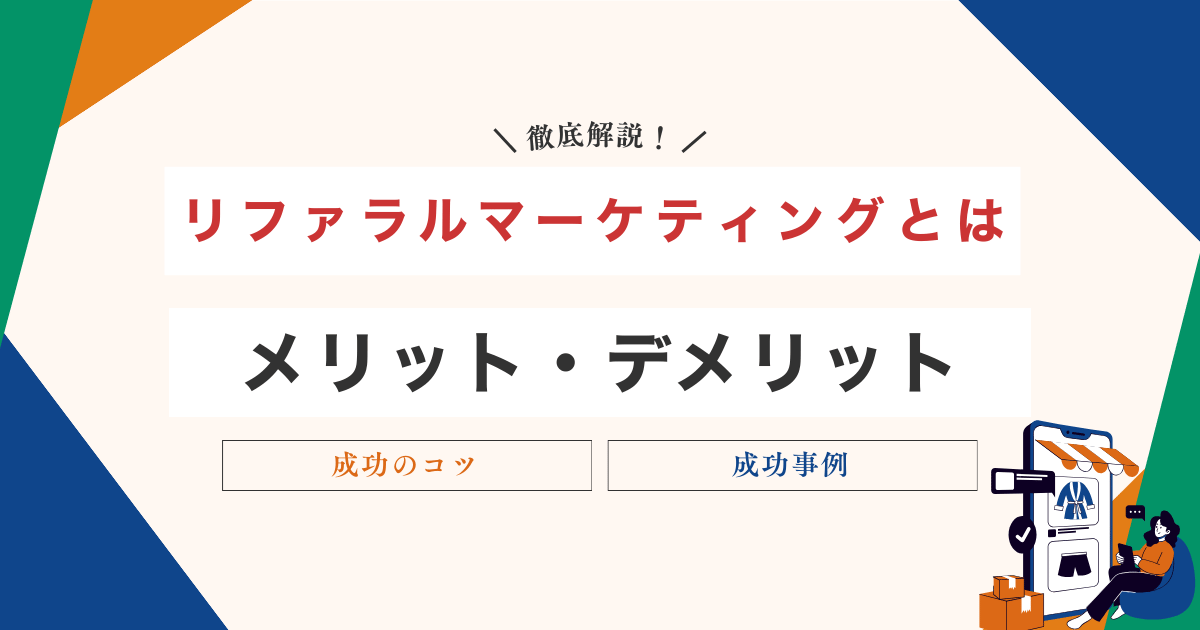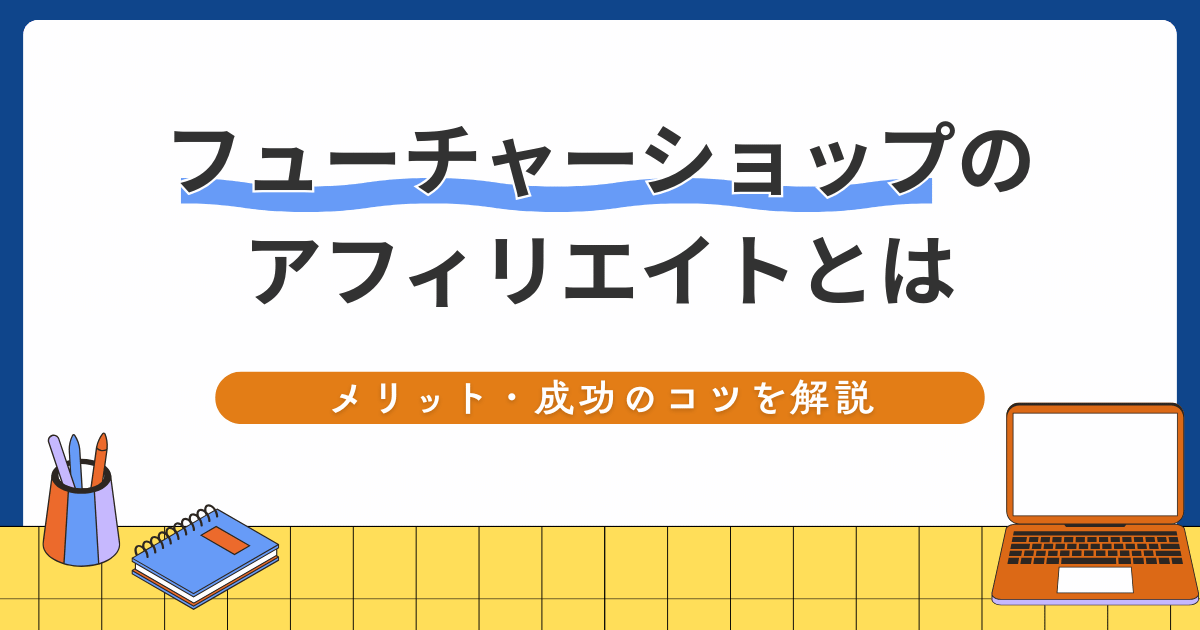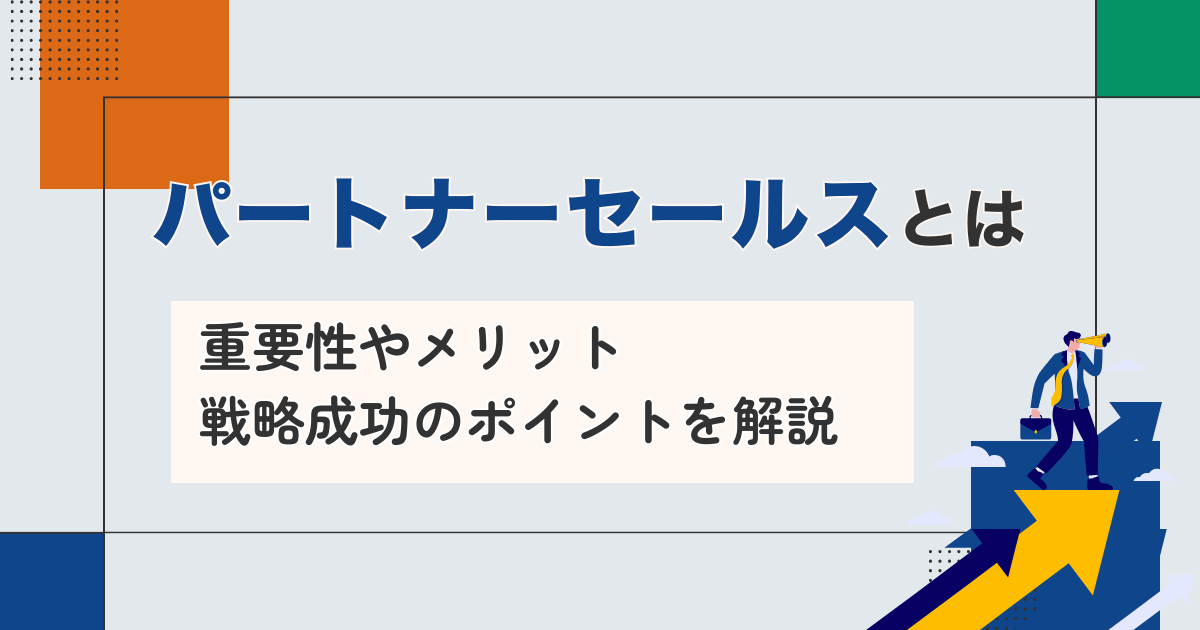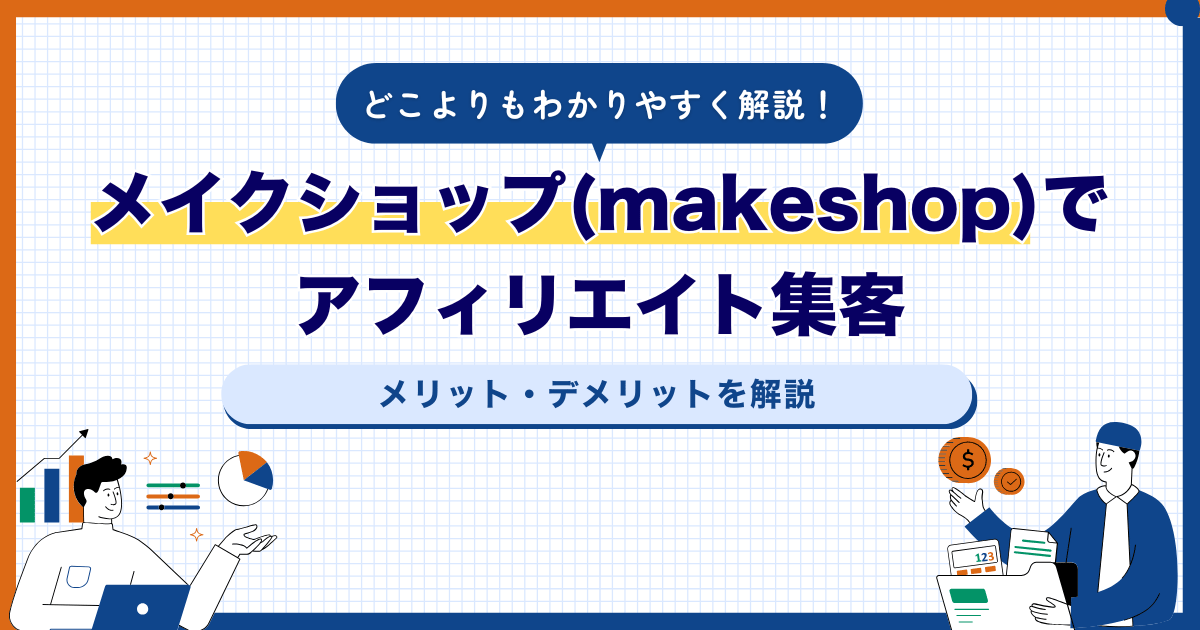企業の成長を支えるマーケティング戦略の中でも、近年注目を集めているのが「パートナーマーケティング(Partner Marketing)」です。
自社単独では到達できない市場へ進出し、他社や個人と協力して価値を共創する仕組みです。
パートナーマーケティングにより、自社だけではリーチできない市場の開拓や新たな顧客価値の創出が可能になります。
スタートアップや中小企業でも成果をあげられることや、パートナーと互いに利益を享受し成長できることから注目されています。
管理コストの増加やパートナー選定の難しさが課題ですが、明確な戦略設計を行うことでパートナーとの信頼関係を築き成果につなげることが可能です。
この記事では、パートナーマーケティングとは何かから、種類やメリットについて解説していきます。
注意点や成功事例を確認して自社の戦略に取り入れる際の参考にして下さい。
パートナーマーケティングとは

パートナーマーケティングとは、他社や個人などの外部パートナーと協力して、商品やサービスの販売・認知拡大を行うマーケティング手法です。
企業単独のリソースだけでは、新市場への進出や顧客接点の拡大には限界があります。パートナーを活用することで、信頼・販路・ブランド力を相互補完し、成果の最大化が可能となります。
たとえば、SaaS企業が販売代理店を通じて顧客を獲得したり、ブランド企業がインフルエンサーと提携して発信力を高めるケースが代表的です。
BtoBでは共同セミナーやコマーケティング(Co-Marketing)が、BtoCではアンバサダープログラムが一般的な形態です。
つまり、パートナーマーケティングは単なる販売の代行ではなく、共に市場を拡大する共創型のマーケティング活動です。
代理店とパートナーの違い
代理店とパートナーとでは目的や関係性に違いがあります。
以下は代理店とパートナーの違いをまとめたものです。
【代理店】
- 主な目的:商品の販売・再販
- 関係性:契約ベース(販売代行)
- 責任範囲:売上・販売目標重視
- 代表例:販売代理店、取次店
【パートナー】
- 主な目的:共創・協業による市場拡大
- 戦略的連携(相互利益)
- 顧客体験・価値創出も重視
- アライアンス企業、共同マーケ先
代理店は販売の代行であるのに対し、パートナーは共に市場価値を作る存在です。
代理店はメーカー・サービス提供者の代理として販売・運用を行いますが、パートナーは対等な協業関係で市場を広げるといった立場の違いがあります。
また、パートナーは相互のリソースや顧客基盤を活かして共創・共販することを目的としていて長期的な市場拡大が期待できます。
受託ビジネスである代理店の場合、意思決定権はメーカー側にあります。自社商材を相手の顧客基盤で広げる共創的マーケティングの要素が強いパートナーとは関係性も異なります。

パートナーマーケティングは他社を利用する施策ではなく、他社とともに成長する仕組みです。
パートナーマーケティングが注目される理由
パートナーマーケティングが急速に重要性を増しています。
その理由としては以下が挙げられます。
- 市場が成熟し、差別化が難しくなった
- SaaSやD2Cなどリレーション型ビジネスの台頭
- 信頼ベースの購入行動が重視される時代へ
- リモート・デジタル化による共創コストの低下
市場が成熟したことで他社との差別化が難しくなり、価格競争・広告競争が激化しています。
自社だけでの広告よりも、信頼関係のある他社と組んで一緒に広めるほうが費用を抑えつつ効率的に顧客に届けることが可能になります。
例として以下が挙げられます。
- SaaS企業が導入支援のコンサル会社と組む
- D2Cブランドが美容クリニックと提携して商品を紹介してもらう
- Web制作会社がSEO会社と協業してワンストップ提案をする
自社だけでは届かない顧客層へ、他社の信頼やネットワークを借りることでアプローチすることが可能です。
また、専門性や信頼性をあげることでもパートナーシップは有効です。一緒に価値を作り共に広げるという考え方がマーケティングに求められていると言えます。
SaaSやD2Cなどリレーション型ビジネスが台頭したことも、パートナーマーケティングが注目される理由です。このタイプのビジネスでは最初の販売より継続して購入してもらうことが大切だからです。
そこで、サポートやアフターケアを他の会社と協力して行うケースが増えています。
ツールが発達して、オンラインで簡単に連携・紹介・支払いができるようになり、誰でも低コストでパートナー施策を始められるようになりました。
顧客獲得コスト(CAC)が上昇する今、広告ではなく信頼で売る構造が注目されています。

たとえば、BtoB SaaS業界ではHubSpotやZoomのように、パートナー経由の売上比率が70%以上を占める企業もあります。
成果報酬型業務提携ツール
について相談してみる
パートナーマーケティングの種類

パートナーマーケティングは、以下の形態が代表的です。
- 販売パートナー(代理店)
- 紹介パートナー
- アフィリエイトマーケティング
- アンバサダーパートナーシップ
- ロイヤルティプログラム
- コンテンツパートナーシップ
- アライアンス(合併)・資本提携
自社の事業モデルに合う形を選定することが重要です。
販売パートナー(代理店)
代理店に自社商品やサービスを販売してもらう手法で、代理店が販売活動を行いやすいように支援をします。自社の直販だけでは届かないような顧客にまで、販売チャネルを拡大することが可能です。
自社だけでなく、代理店に売上以外に自社商品を扱うことにメリットを感じてもらう必要があります。
販売のためのノウハウを提供を提供し、必要な知識や学習できる環境を整えることが重要です。
紹介パートナー
自社サービスを顧客に紹介してもらい、成果に応じて報酬を支払うモデルです。
営業コストを抑えつつ、信頼経由のリード獲得が可能。
例としては会計事務所が中小企業に業務ツールを紹介するケースなどがあります。顧客が信頼している事務所からの紹介であるために、商談到達率と受注率が高いことが多いです。
短期的に成果が出やすいですが、案件被りや紹介順序の衝突が起きやすいのには注意が必要です。承認ルールの明文化が不可欠となります。
アフィリエイトマーケティング
Webメディアや個人が紹介リンクを設置し、成果に応じて報酬を得る方式です。
SaaSやECで広く利用されています。
アフィリエイターは特定の分野やテーマの専門性が高いことが多く、そこで紹介された商品やサービスは信頼されやすく興味を持たれやすい傾向があります。
成功報酬型の仕組みなので、広告費をおさえつつ効果的なマーケティング戦略を展開することができます。
適切なASPやアフィリエイターの選定や運用の手間が課題となります。
アンバサダーパートナーシップ
自社ブランドのファン・利用者がブランドの体験を語り宣伝活動を担う仕組みです。
アンバサダーは企業とは独立し正直な意見を発信するので、信頼性が高くUGC(ユーザー生成コンテンツ)との相性がよいという特徴があります。
例えば、D2CのヘビーユーザーがビフォーアフターをSNSで投稿することで、自然検索と指名検索が伸びるといった効果が期待できます。
ステルスマーケティングとならないように、明示的なPR表示とガイドラインが必須となります。
ロイヤルティプログラム
販売代理店・紹介者・アライアンスパートナーなどが、自社にどれだけ貢献したかを可視化し、その貢献に応じてランクや報酬・特典を提供する仕組みです。
もともとは顧客に特典や報酬を与えて、再購入など促すポイント制度などで使われてきましたが、企業間の信頼と貢献度を高める制度として長期的な関係を構築するのに役立ちます。
売り上げや顧客満足度などでランク分けをして、パートナーのモチベーションアップや離脱防止・売り上げの安定化を図ります。
一度きりの取引ではなく、一緒に成長し成功を共有していく関係を作ることを目的としています。
コンテンツパートナーシップ
お互いの強みや専門知識を活かして、一緒に記事・ウェビナーなどのコンテンツを作る協力関係です。価値のある情報の共創を行います。
自社だけでは語れない分野を他社の知見で補い、相互に顧客層を共有して新しい層へのリーチを目指します。
よくあるコンテンツパートナーの形は以下です。
- 共同記事・ブログ:双方の専門知識をまとめた記事
例)「〇〇社 × △△社が語る、ECの未来」 - 共同ウェビナー:両社が登壇して知見を共有
例)SEO×広告 運用ノウハウ共有セミナー」 - 共同資料・ホワイトペーパー:資料を共作し、相互ダウンロード促進
例)「マーケティング担当者の教科書」共同制作 - 寄稿・インタビュー:片方のメディアにもう一方が登場
例)「顧客成功の裏側」特集インタビュー - SNS・動画コラボ:相互PR・相互発信
例)インスタライブ、YouTube対談など
共同でホワイトペーパー・セミナー・動画を制作し、双方のリードを共有します。 コマーケティング(Co-Marketing)の一環としておこなわれます。
コマーケティングとは
コマーケティングとは、他の会社と協力して一緒に集客や販促を行うことです。互いの知名度や得意分野を活かして一緒にイベントや広告などを実施して両方の会社の売り上げや認知を高める取り組みです。
コンテンツパートナーは一緒に情報発信やコンテンツ制作を行う協業のことで、一緒に販促・マーケティング施策そのものを行う協業であるコマーケティングとは目的が異なります。
集客やリード獲得など、直接的なビジネス成果を狙うことを目的としているのがコマーケティングです。
アライアンス(合併)・資本提携
アライアンス・資本提携は、一緒に市場を作るために経営レベルで組むパートナーシップのことです。より戦略的に企業価値を高める形態。技術共有や共同ブランド立ち上げなども含みます。
アライアンスとは業務上の連携のことで技術・販促・サービスなど、互いの弱点を補い、より大きな価値を生み出すことを目的としています。
資本提携は片方または双方が相手企業に出資して、資金面での関係を含める協力関係のこと。互いの経営や方向性を長期的に連携する狙いがあります。
市場の拡大や競争力の強化・新サービスの開発を目的とし、長期的な事業の成長を目指します。
パートナーマーケティングのメリット
パートナーマーケティングのメリットは以下が挙げられます。
- 直販ではリーチできない市場の開拓ができる
- 新たな顧客価値の創出
- 少人数で成果を大きく向上できる
- パートナーと互いに利益を享受できる

短期的な成果より、信頼関係と再現性ある仕組みづくりができるのが最大のメリットです。
直販ではリーチできない市場の開拓ができる
メリットとして、自社だけでは届かない業界・地域・顧客層に、パートナーの販路や顧客網を通じて効率的にアプローチすることができることがあげられます。
これは、パートナーの既存の信頼関係に便乗することができるからです。到達コストが低く信頼を早く得ることが可能です。
例としてはSaaS企業が地方代理店経由で中小企業を開拓することがあげられます。
自社に欠けている接点を埋めるパートナーの選定が重要です。
新たな顧客価値の創出
互いの強みを組み合わせることで、単体では作れない解決策を生み出すことができるのもメリットです。
例えば、会計ソフトに請求の自動化・銀行との連携を掛け合わすことで、経理の月次締め時間を50%削減することに成功したケースがあります。美容液のECに専門家監修の使い方動画・定期プランを結合させ、継続率が向上したという例もあります。
このようなパートナーマネジメントによる利用体験の掛け算によって、顧客の満足度の向上が期待できます。
少人数で成果を大きく向上できる
少人数で成果を大きく伸ばせることもメリットの一つです。
人的リソースを増やさずに、外部の販売・運用力を使って成果を拡大することができるからです。
パートナーの既存の仕組みを使うことで、固定費を増やさずに運用を分業することができます。
中小企業やスタートアップ企業でも、パートナーマーケティングによって全国規模の展開をすることが可能になります。
パートナーと互いに利益を享受できる
自社とパートナー双方にとって収益・実績・ブランド価値が上がることもメリットです。継続的な協業につながっていきます。「Win-Win」の関係性が築ければ、長期的・安定的な収益構造になるでしょう。
パートナーマーケティングによって、互いに今までに獲得できなかった市場での事業成長を実現可能です。
成果連動の報酬や共同知財を設計することで、持続的な事業の成長やブランド価値の向上につながっていきます。
パートナーマーケティングのデメリット
パートナーマーケティングは多くのメリットがありますが、デメリットも存在します。
- パートナーの管理コスト増加
- 営業プロセスの不透明性
- パートナー選定の難しさ
それぞれについて確認しておきましょう。
パートナーの管理コスト増加
パートナーの管理には、契約・報酬・教育などの運用コストが発生します。
特にパートナー数が増えるほど管理の仕組みが重要になります。
問い合わせ対応や資料カスタムなど、スケールに比例して雑務が増加。システムや人的リソースが不足していると、対応が遅くなったり情報が分散したりして業務効率の低下やミスにつながります。
これを防ぐためには最低限の共有ポータルを作成し、契約の段階で監査・是正条項を明記することが有効です。
導入の手順やFAQなどを用意することで、パートナーの満足度が向上します。
営業プロセスの不透明性
営業プロセスが不透明であることもデメリットとしてあげられます。パートナー経由では、顧客接点が間接的になるので商談情報が得にくいからです。
これにより、二重提案や過剰な値引きが起きたり、契約条件に行き違いが起こる可能性があります。ブランド毀損や取りこぼしの発生につながり、結果的にパートナーの不信感につながる恐れもあります。
対策としては、プロセスを共通で見ることのできる仕組みやブランドガイドラインの作成が必要となります。
違反時の是正手順やルールを徹底し、プロセスの透明性を保つことが重要です。
パートナー選定の難しさ
パートナーマーケティングでは、適切なパートナーの選定が重要です。価値観や顧客層が一致しない企業と提携すると、ブランド毀損のリスクがあるからです。
ターゲット市場や提供価値が曖昧なままだと、パートナーとのミスマッチが増える可能性があります。運用コストだけが上がり、ブランドの一貫性や顧客体験が崩れるリスクもあるのです。
選定の際は顧客基盤の一致や過去の実績・サポート体制などの基準をはっきりとさせ、契約条件に未達時の是正や解約条項などの明記が必須です。
契約前に価値観・顧客層・KPI基準を明確化しておくことが重要です。
成果報酬型業務提携ツール
について相談してみる
パートナーマーケティングを始める際のポイント
パートナーマーケティングを始める際は、明確な戦略設計を行うことが成功の分かれ目です。
- 適切なパートナーの選定
- 目標の設定
- パートナーへの期待値の明確化
- 適切な報酬制度の制定
- パートナーのサポート体制の構築

パートナーマーケティングは単なる協力する仕組みではなく、信頼をもとに一緒に成長する仕組みです。だからこそ、パートナー選定・ルールの明確化・サポート体制の充実が重要です。
適切なパートナーの選定
適切なパートナーを選ぶことが重要です。
価値観や長期目標が一致していない場合、費用ばかりかかって成果につながらないといった結果になってしまうからです。
自社と相性の良い相手を選ぶことが大切。選定の際には、
- 顧客のターゲット層が同じ
- 信頼性が高い
- 販売力や知名度がある
- 競合ではない
といったポイントをおさえましょう。
例えば、美容液ブランドならエステサロンや美容家・化粧品販売店などは相性が良いです。
顧客層・販売力・ブランド親和性だけでなく、価値観や長期目標が一致するかどうかも確認します。
目標の設定
目標を具体的に設定することも重要です。ゴールが曖昧だと継続できず成果につながらないからです。期間別・指標別(売上・CV・リード数など)でKPIを定義しましょう。
例えば、
- 〇ヶ月で新規顧客100人増加
- パートナー経由の売り上げ20%
- 毎月共同キャンペーンを1回行う
など、どんな成果を目指すのか明確にします。
「何を・いつまでに・どれくらい」か数字で決めておくと成果を比較する際に役立ちます。
成果共有型の管理体制を構築することが重要となります。
パートナーへの期待値の明確化
パートナーの役割は明確にしておくことが重要です。互いの担当と責任を決めておくことでトラブルを防ぐことができるからです。成果の定義を共通化することも重要です。
広告・SNS発信や共同セミナーはどちらがやるかなど、自社・パートナーの役割を明確にしましょう。
教育・マニュアル・ナレッジ共有を徹底することが重要です。
適切な報酬制度の設定
パートナーが活動しやすいように、報酬のルールをシンプルにしておくことが大切です。
どんな条件でいつ、いくら支払われるのかが明確だと、信頼関係を長く続けることができるからです。
固定報酬と成果報酬のハイブリッドが主流ですが、SaaS業界では月額課金の継続率連動型も増加しています。
シンプルで公平なルールによって信頼関係を築くことが可能です。
パートナーのサポート体制の構築
パートナーのサポート体制をきちんと構築することも重要です。
パートナーは自社の商品を売ってくれる仲間。商品知識や販売ノウハウを共有し、売りやすい環境を作ることが成果につながるからです。
サポート体制の例としては、
- 商品マニュアルや動画を共有する
- 定期的に勉強会を開く
- 相談窓口をつくる
- 宣伝素材や写真をまとめて渡す
などがあげられます。
パートナーポータル・専用ダッシュボードなどで活動を支援したり、定期的な勉強会やイベントを開催することも有効です。
成果報酬型業務提携ツール
について相談してみる
パートナーマーケティングの企業事例
パートナーマーケティングによって成長・成功した企業事例を紹介します。
HubSpot

画像引用:HubSpot
HubSpot は、CRM(顧客関係管理)やマーケティングオートメーションを提供する世界最大級のSaaS企業として知られています。
「パートナープログラム(Solutions Partner Program など)」を早期に立ち上げ、代理店・実装支援会社・技術パートナーなど多様なパートナーを巻き込んで成長してきました。協業による販路拡大・共創のお手本としてあげられています。
パートナーを通じたチャネル拡大を体系化し、直販だけでは届きにくい市場へのリーチを可能にしました。
あるパートナーはHubSpotのプログラムに参加後、リード数が40%増、売り上げが50%増となったと公式サイトで紹介されています。
Zoom

画像引用:Zoom
Zoomは自社で直接セールス・販売するモデルが中心でしたが、パートナーを通じて販売・導入サービスを拡大するモデルに転換し成功した例として有名です。
チャネル(パートナー経由)重視に戦略を転換し、パートナープログラムを設計、パートナーに対しての認定・報酬・支援を体系化しています。教育・イベント・BtoB企業と提携し、導入支援パートナー制度を展開。
パートナーが活動しやすいように手続きのプロセスを簡単にし、様々なパートナーを戦略的に活用できる体制を整えています。
これにより、パートナー営業予約が2020年には前年対比7倍、日本市場ではチャネルパートナーが約40%を占める地域もあると公表されています。
Shopify

画像引用:Shopify
Shopify は、EC(電子商取引)プラットフォームとして世界中で多くの企業・個人商店に利用されています。
「パートナー制度(Shopify Partner Program)」を通じて、サービス提供者(開発者・デザイナー・代理店)やテーマ・アプリ開発者、紹介者などが Shopify のエコシステムと協業し、互いの価値を高めていることからパートナーマーケティングの成功モデルとして言及されることが多いです。
デザイン・開発・マーケ・販売といった多様なパートナータイプを設計していますが、パートナーにも明確なメリットが提示されています。例としては、テーマ開発やアプリ販売で個人も収益を得られるモデルを確立していることがあげられます。
パートナープログラムの階層化やトラックを整備し報酬・特典が存在するので、質を担保した協業を保ちやすくなっています。
まとめ
パートナーマーケティングとは、 自社のリソースを補うパートナーと共創で市場を広げる戦略です。
新市場の開拓やリソースの補完だけでなく、顧客の信頼を獲得することが可能になります。
代理店や紹介パートナー・アフィリエイトなど、パートナーマーケティングには種類があるので自社の事業モデルに合うものを選定しましょう。
小規模な企業でも、適切な設計を行えば大きな市場影響力を得ることが可能です。広告費よりも信頼関係への投資をすることが今後の競争力を左右していくでしょう。
パートナーとともに成長する共創マーケティングを戦略に取り入れましょう。